読み物
time piece ①


石井美百さんは、神戸を拠点に青竹細工をされています。
彼女の技術的なルーツは大分竹細工。
岡悠さんは、京都宇治田原で白竹細工をされています。
彼女の技術的ルーツは京竹細工。
竹細工の産地は今も日本中に点在し、以前はもっともっとありました。
寒暖差のある日本では土地ごとに生育する竹の種類に違いがあり、同じ竹でも青のまま使うところもあれば、白くして使う場合もあります。
お二人が使う青竹と白竹は、同じ真竹。
青竹は伐採した真竹そのものの色を生かした素材で、白竹は真竹に含まれる油分を抜き天日に晒すなどして色を抜いた素材のことを言います。
同じ真竹でも、青と白では、硬度やしなやかさなどの性質、材料づくりのタイミングや保管の取り扱いなどは異なります。
そして見た目で分かりやすい「編みの模様」。
竹細工の基礎となる編み模様(六つ目、四ツ目、網代等々)こそ共通しますが、そこからまた応用され生み出された編み図の発展を見ると、大分系統独自のものと京都系統独自のものとではそれぞれかなり特色があり、個性ある美しさと面白さを楽しむことができるでしょう。
土地ごとの文化の違いから始まり、どこでどんな人々にどのように使われていたかで求められるもの、良しとされるものはその都度変化します。
先人たちの竹の仕事がこれまで長く長く積み重ねてきた時間。
流れ流れて現代。
竹の仕事をする石井さんと岡さんがそれぞれ積み重ねてきた時間。
時のかけらが降り積もり結集し編まれた一目一目の中には、目に映る以上のものが深く濃く編み込まれているようにも感じます。
今回の小さな催しでは並ぶ数は少ないですが、その代わりに作られたものたちとじっくり対話するような場をご用意いたします。
Fail better,Wonderful happens. ⑤


はしもとさちえさんの銀彩のボウル。
個展用に制作したものの手元に戻ってきたという。
それでも、
はしもとさんの象徴とも言える「彫り」は、このボウルにはない。
姿は優雅な曲線を描き、肌はすべて銀彩をまとっている。
彼女が長い間尊敬してきた作家へのオマージュも寄せられている。
古き佳きものを写すことで、
銀彩の金属的でクールな色合いと、




森谷和輝|ロート

グラスを作るつもりが溶けすぎてできた形だそう。
ロートとして使えて、
背景に溶けてしまいそうなくらい透き通っている部分と、
実験器具として作られている耐熱ガラス製の漏斗とは異なる趣。
何かに似ていると眺めていると、はたと思い当たった。
Fail better,Wonderful happens. ④


su-nao home|リム深皿rm-4
su-nao homeの松本圭嗣さんから届いた今回のリム深皿rm-4。
規格内と規格外について、作り手は各々の物差しを心と目に携えて
このリム皿たちはいつもよりも釉薬を厚くかけてしまったことで、
それでも焼き上がりに美しく感じる部分が多く、工房の隅に数年間
su-nao homeさんの〈黒の器〉は常に凪いでいる夜の水面のよう。
その黒が、この時は風に吹かれざわりとさざめいた。
黒はより黒く深みを増した。
目を凝らすとリム皿の釉肌はいつもよりも饒舌で、豊かで芳醇な階



高木剛|カイラギ茶碗
カイラギとは漢字では梅華皮と書いたり梅花皮とも書いたりする。
ものの本によると
「 梅花皮はインド洋などに生息する特殊なエイの皮に漆を塗って研ぎ
とある。
こちらではそろそろ梅の見頃も終盤。
花を眺めながら高木さんの茶碗のことを思い出していた。
茶碗をお蔵入りさせていた理由は〈釉景不足〉ということだった。
高木さんが求めていたよりも淡味ということなのかもしれない。
一方で淡い味わいを好む人もいる。
お茶を味わう時間を経るごとに、




とりもと硝子店さん|大鉢

ポンテ跡がきつく泡の模様にも思うところあって眠らせていたということだった。
大きく、素材の存在感が際立つ。
とりもと硝子店さんが作る透明なガラス。
澄み切っている、悠然と。
光と水をたっぷりと備えて。
静かでありながら、確かなエネルギーを発している。
無数の小さな泡粒は、
仕上がりに思うところがあっても、




Fail better,Wonderful happens. ③


境知子|刷毛ピッチャー
掠れたようになった表面。
境知子さんの刷毛ピッチャー。
焼成温度が高過ぎたせいか、表面に塗った化粧土が飛んでいたり焦
知子さんが形づくるものはいつも独特の〈まるみ〉〈ふくよかさ〉
生きている動植物の輪郭のそれに似ている。
ピッチャーを背面から見る。
掠れは鳥の毛羽立ちを思わせ、何かの生物のまるい背中がそこにあ



境道一|ミモザ釉蓋物
炎の力は大きい。
私たちが想像している以上に。
境道一さんのミモザ釉蓋物。
平らかに作ったはずの蓋は、焼成時の炎の熱によって水分を奪われ
一方で釉薬は炎によって化学反応し、美しい色を生み、表情を作り
わずかにいびつな蓋は、炎の力の大きさと無限の魅力を伝える痕跡
うっすらとだが開いている蓋の口からは、火の国の見知らぬ音楽が
もしくは人には解することのできない火の言葉が耳を澄ますと聴こ
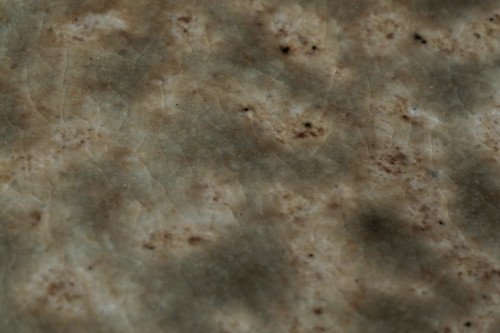


須原健夫|真鍮皿
朽ちてもなお消えず、新たな姿を獲得し続ける。
須原健夫さんの真鍮皿。
玄妙なる経年変化を発しながらも、この緑青が周りを汚すかもしれ
緑青(ろくしょう)はいわゆる錆の一種。
発生しそのままにしておくと徐々に広がり続ける。
真新しい明るい金色の光がゆっくりと鈍く沈み緑青を帯びるという
その時間ごと手のひらに乗せる。
こぼれ出す緑青に侵食されながら、尽きることなく美しく変貌を遂



Fail better,Wonderful happens. ②


井上茂|青白磁鎬碗
昔の作品。
薪窯焼成の青白磁鎬碗。
割れあり、降灰あり。
透き通る青白磁。
ゆったりふっくらした碗型に、入れられた鎬ののびやかさは明朗な
薪を贅沢に使っていた頃の作品は、井上茂さんのもとでずっと眠っ
今はもう、こんな風に焼くことはないという。



小野陽介|赤灰釉ピッチャー
小野陽介さんの赤灰釉ピッチャー。
釉調や高台の始末に思うところがあって、手元に残していたそう。
裏返すと未完の高台には粗削りな迫力が。
流れすぎたという釉薬も夕闇のような景色が広がり、釉肌はしっと
作者の想定通りにいかなかった物。
思惑とは異なる美しさ。



近藤康弘|ボーンホルム島原土スリップ模様皿
近藤康弘さんの大きめのグレーの長方皿。
ボーンホルム島原土スリップ模様皿。
静かな存在感に満ちている。
5年ほど前にデンマークのボーンホルムに滞在した際の作品。
土中の含有物が焼成時に爆ぜて釉が剥がれたものの、気に入ってず
陶土や釉薬などの材料をすべて現地のボーンホルムで調達し、現地
その土地に滞在して呼吸し、その土地で採った原料があって作るこ







